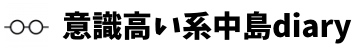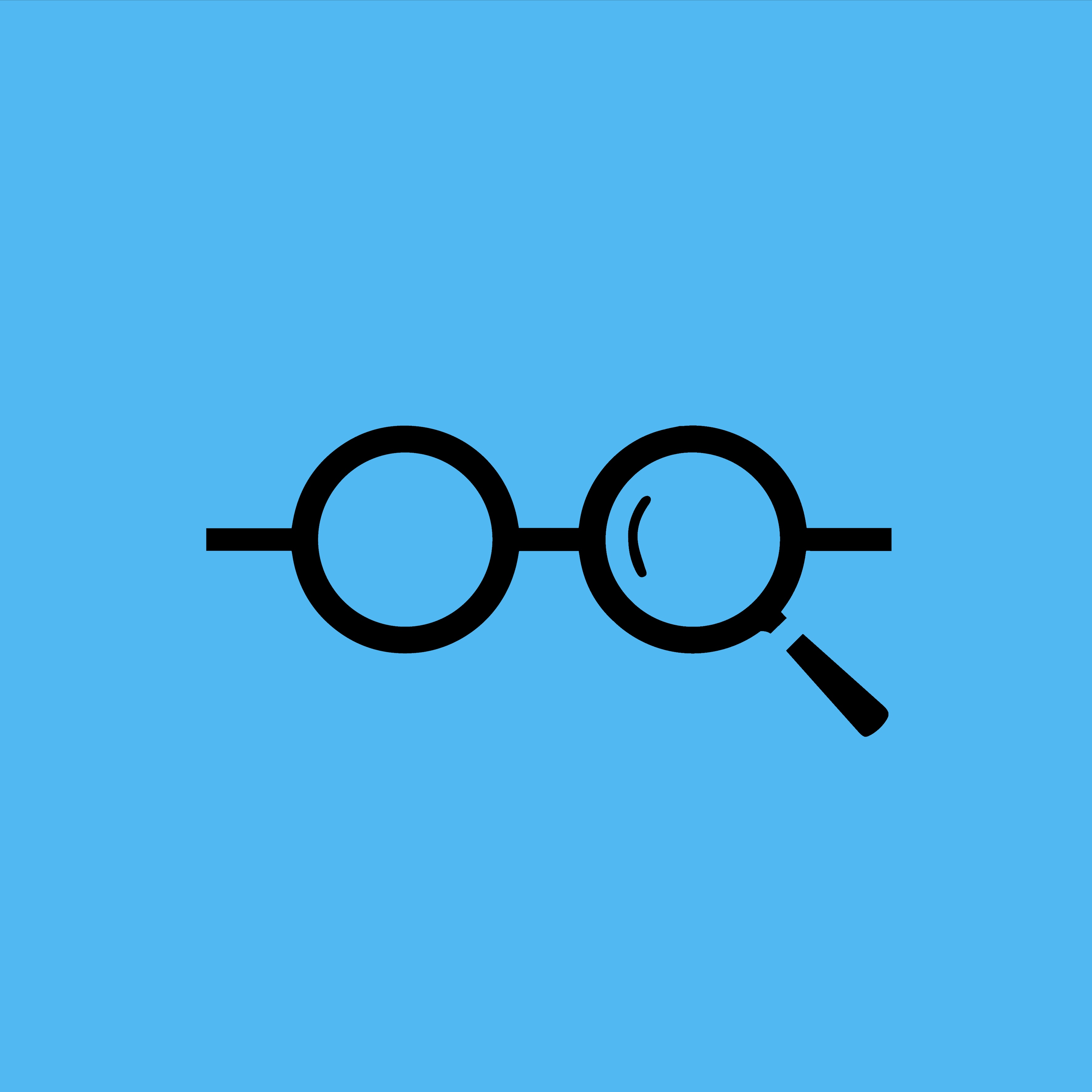とある週末。いつものクラブで一人酒を飲み、適当に近くの外国人や女の子と話しながら流れる音楽に合わせ踊っていた。
残念ながら全く音感のない僕は、ヒットチャートに合わせて不器用に体を動かす。
右足を一歩前へ。その隣へ左足を持ってくる。次に右足を後へ、また左足を後ろへ。そんなダサい動きを繰り返し、頭を音に合わせ動かしながら一応音楽に乗っていた。
そんなとき後から急に声をかけられた。
「おまえよくここくんの?」
20代後半くらいの男だった。青のネクタイにピシッとしたスーツを着て、脇に黒のクラッチバッグを挟んでいた。おそらく仕事帰りだろう。
クラブでは知らない人に声をかけるのなんて日常茶飯事だ。
僕は最近来るようになったと答えた。
「そうなんだ。慣れてんのかと思ったわ。おまえ俺とコンビ組まね?」
彼はそういった。一瞬なんのことか分からなかったが、どうやら僕と一緒にナンパをしようという意味だった。
彼はかなり常連らしく、ここでの振る舞い方を心得ているようだった。
物は試しだ。僕はいいですよと答え、彼とLINEを交換しジントニックで乾杯をした。
クラブに来る人の大半がナンパをしにやってくる。僕も最近は女の子に声をかけ、仲良くなることもあった。だがいつも1人で来て1人で楽しんでいるので、2人で行動するのはこれが初めてだった。
彼はイノウエと言った。彼曰くナンパについては百戦錬磨で、いつも行く友人が来ないので代わりに僕に目をつけたということだった。
グラスに注がれた酒を一気飲みし、僕は彼について行った。
彼の手口は鮮やかだった。クラブに来る女の子は大抵二人で来ている。女の子たちを見つけてはイノウエは自然に近づき声をかけ、あとから僕が会話に加わるという形でひっきりなしに誰かと話した。
「ここ入って思ったんだけど君が一番可愛いわ。よくここ来るの?」
お決まりの文句でイノウエは話しかける。
イノウエは坂口健太郎似の塩顔のイケメンだった。人は褒められると悪い気はしない。ここにいる人も例外ではない。とくに来慣れていない人は初めは緊張した面持ちで微妙な反応を示しながらも次第に打ち解けていく。
「こいつ大学の後輩の中島って言って」
話が進んだところでイノウエは僕を紹介する。この後輩というのは完全に嘘だ。しかし嘘も方便とはよく言ったもので、機転の利いた小さな嘘はコミュニケーションを盛り上げるのに大いに役立つ。そして僕は全く人に自慢できない才能のひとつに、その場で適当な作り話を作って最もらしく語る能力を授かっていた。適当にイノウエの話に合わせ話を作り、ウケを取る。お互いの心理を探り、打ち解ける話題を見つけていく。下心がないと言えば嘘になるが、こうして初対面の人と話をし、聞いたことのない話を聞くのは本当に楽しい。
こんな感じで自然な流れで僕らは会話し、盛り上がり、連絡先を交換してはまた次の女の子と話した。
蝶のように舞い、蜂のように刺す。
イノウエはまさにその言葉を体現していた。
人でごった返すフロアを身軽に立ち回り、すっと間に入る。自然な流れで話し始め、いつの間にか和んでいる。
僕も彼のあとをつけ、一晩中話し続けた。
大学生、専門学生、OL、看護師、いろんな人がいた。みんなとても優しく、僕らは大いに楽しんだ。
気がつくとLINEの連絡先が20件も増えていた。僕は忘れないように相手の歳とあった場所、日付をメモした。いままでの経験で、酒を飲んだ翌日に誰のか分からない連絡先が新たに登録されていて、不審に思って消したことが何度もあったからだ。
フロアの熱気もピークを超えた午前3時、イノウエは外を散歩しようと僕を連れ出した。
夜中の冷気が体にしみた。火照った体はすぐに冷やされ、体に染み付いたさっきまでの熱気と耳に残ったEDMが洗い落とされていく。酔いと共に夢から醒め、深夜とは思えないくらい煌々と輝いた繁華街の一角に、僕とイノウエは立っていた。
近くの公園に向かいながら、イノウエは僕にこんなことを聞いた。
「お前、どういうところで働くの?」
もちろん大学を出たら働く気ではいたが、具体的にどんな職種に就くかは決めていなかった。逆にイノウエにどんな仕事をしているのか聞いたところ、彼は商社で働いているということだった。
「商社って言ってもそんな大したもんじゃないけどね。でもいろんな国行けるからほんと楽しいのよ。」
イノウエの喋り方は少々訛りがあった。出身はどこか尋ねたところ、石川から専門学校を卒業したと同時に上京してきたらしい。
「お前、東京ってどうよ。楽しい?」
イノウエは再び僕に問いかける。
僕自身こういう都会で遊び始めたのは大学生になってからだった。
確かに東京にはなんでもある。特に地方の大学に行った友達に話を聞くと、僕はここに残ってよかったなと思うことが多い。決して地方暮らしを馬鹿にする気はないけど、やっぱり日本の首都は東京なのだ。いろんな面白いものが集まってくる。
さっきのクラブだってそうだ。色々なところからお祭り騒ぎや出会いを求め、人が集まる。何か刺激に定期的に触れられる生活は飽きない。
僕はとても楽しいと返事をした。ちょうど公園につき、僕らはベンチに腰掛けた。
「ならよかったよ。でもね、俺はもう東京はいいかなあ。」
ふうと大きく息をすい、イノウエは滔々と語り出す。
「ここにいる大人はね。甘えてる奴が多いのよ。何かに依存して生きている。東京ってね、そういう奴らがね、多い気がするの。だってね、俺の会社にも20後半で実家暮らししてるような甘ったれた野郎がたくさんいるのよ。あと会社名とか学歴とかね、肩書きでデカイ顔してる奴とかね。そういうね、何かに依存して生きてる奴が俺は大嫌いなんですよ。だから」
そういうとイノウエは前髪をかき揚げ、天を仰いだ。
「俺、会社やめて東南アジアに行ってビジネスしようと思ってるのよ。」
イノウエはまっすぐに遠くを見つめている。
「あそこで暮らしてる人はね、頼るものも何にもない状況で生きてるの。だから自分の力ででけえことやって貧乏から抜け出そうと頑張ってるのよ。はっきり言って成功するか地べたを這うかのどちらかだから。何にも依存しないで生きるってのはそんくらい大変なことなんだよ。
この前な、家の近くのコンビニに仲良いフィリピン人の兄ちゃんの店員いるんだけど、ちょっと話したのね。
そしたらそいつがよ、”今はお前の方が俺より稼いでるだろうけどすぐにお前なんか抜いてやるからな”って笑顔で言われたのよ。
でもそれって冗談でも何でもなくてね、本当に俺らなんてあっという間に抜かされちまうよ。
だってそいつは20で国を出て知らない場所で稼ぐ決断したんだよ。お前の周りにそんな奴いるか?東南アジアにはね、若くして決断してバンバン世界に出て0から上に登ろうとしてる奴が山ほどいるのよ。
そんな奴らに俺らが勝てるわけないんだって。俺はそういう意欲のある人たちを助けたいんだ。」
そういうとイノウエは立ち上がり、大きく背伸びをした。
「それにあっちの女は日本の子よりも俺の好みなんだ。」
彼は僕の方を振り返り、ニヤッと白い歯をのぞかせた。
僕らは何かに”依存”して生きている。確かにそうだ。バイトもせずに親の金で一人暮らしをし親の金で留学に行き親の金で良いスーツを作って就活をする。大学にはそんな甘ったれた奴がわんさかいる。でも彼らは経済的に余裕のある家に生まれたからそういった生活を享受できているわけで、そういう環境には生まれなかった僕の僻みにすぎない。だが僕は自分の力で何かを切り開こうとしている人の方が好きだ。
”現状維持では後退するばかりである。”
かつてウォルト・ディズニーはこう言った。僕は常に何かと闘い、周りを出し抜き、少しでも上を目指さなくてはならないと思っている。人よりも上に立ちたい。そういう思いが僕にはあった。でも大学に入り予想以上に生ぬるい周りに流され、その情熱は失われつつあった。普通に単位を取り普通に就活し、普通に卒業する。それだけでも不自由のない生活は得られるだろう。だけど、そんな平凡な生活は僕の求めているものではない。イノウエのように上を目指し、世界に飛び出し勝負を賭ける。僕が望んでいたのはそういうスリルのある生活だった。彼の東南アジアでビジネスをしたいという夢を聞いて、僕の眠っていた想いが呼び覚まされた。
近くの自販機でコーヒーを買い、2人で最後の乾杯をした。オール明けにも関わらず、イノウエの顔はやつれていない。彼の生命力がその顔にみなぎっていた。
ゴミ箱に缶を捨て、僕らは駅に向かって歩き出した。
三月の明け方、東京の空はどこまでも澄み渡り、僕らの出会いを祝福していた。